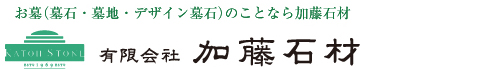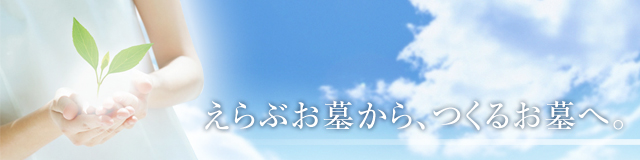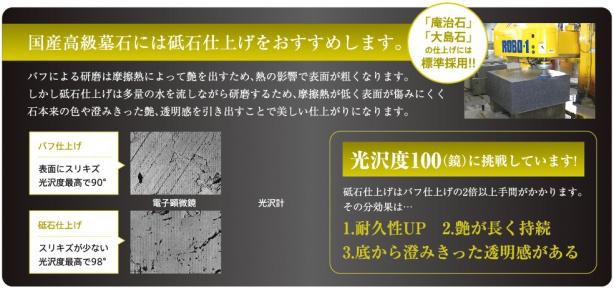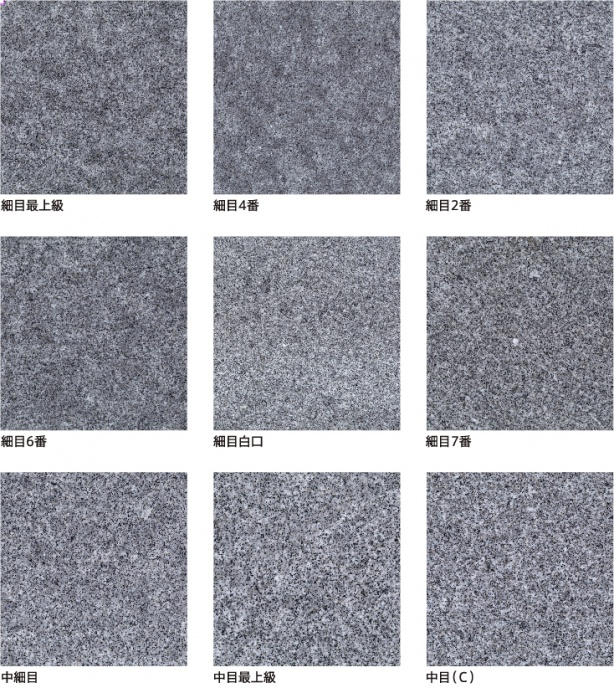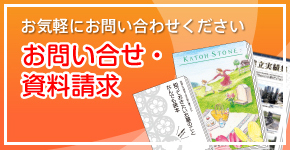これから建てるお墓について
これからお墓を建てる際にいえることは、どういうお墓にするかは基本的に自由である、ということです。
お墓は決まりごとで建てるものではありません。どういう墓が一番いいかは誰にも分かりません。
最後は建てる方ご自身が、死者のことを想い、家族のことや自分のことを考えて決めるものです。
我が家だけの特別のお墓、と感じられるお墓作りはどなたにも当てはまるものと考えます。
もちろんそれぞれの墓地の決め事やルールがあると思いますのでその条件の中でつくらなければいけませんが。
とにかく堅く考えずに、お墓参りをしている自分の姿や家族の姿を頭の中でイメージして固定観念にとらわれずに決めていくことです。
一番大事なことを忘れずに考えていけば、きっと最高のお墓作りができると思います。